 林清登切手コレクションは、1871年(明治4)から1989年(平成元)年に発行された1900点以上にも及ぶ切手を中心とする郵便関連資料です。収集家 林清登氏のご遺族より1994年(平成6)に当館に寄贈されました。日本郵便切手、中国郵便切手、韓国郵便切手を中心に年賀状や暑中見舞い、記念はがきなども含み、長年に渡り、数多く収集された貴重なコレクションです。
林清登切手コレクションは、1871年(明治4)から1989年(平成元)年に発行された1900点以上にも及ぶ切手を中心とする郵便関連資料です。収集家 林清登氏のご遺族より1994年(平成6)に当館に寄贈されました。日本郵便切手、中国郵便切手、韓国郵便切手を中心に年賀状や暑中見舞い、記念はがきなども含み、長年に渡り、数多く収集された貴重なコレクションです。
日本での切手の発行は、イギリスで世界最初の郵便切手が誕生してから31年後の、1871年に始まりました。それまで民間の飛脚屋に委ねられていた郵便業務が官営の新式郵便制度に切り替えられ、この機会に初めて4種の郵便切手が発行されました。それ以降、明治、大正、昭和の各時代の世相の様子をあらわす数多くの切手が発行されてきました。
本展では、これらの切手や郵便関連発行物を時系列で展示します。モチーフや色合いの美しさとともに、時代ごとに特有の役割など、多くの見どころのあるコレクションをお楽しみください。
会期:3月7日(木)~5月12日(日)
※会期中、一部作品の入れ替えがあります
(前半:3月7日(木)~4月9日(火)、後半:4月11日(木)~5月12日(日))
休館日:3月13日、21日、27日、4月3日、10日、17日、24日、5月7日、8日
開館時間:10:00~18:00
入館料:一般370円(260円)、小・中学生160円(110円)
※( )は10名以上の団体料金
※諏訪6市町村に在住・在学の小・中学生、岡谷市内に在住・在学の高校生は無料です
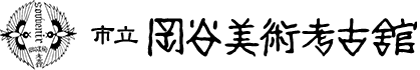


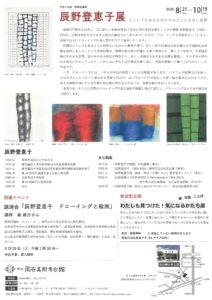






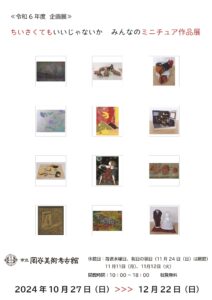
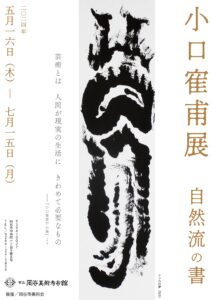
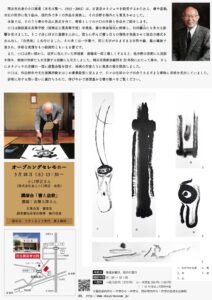

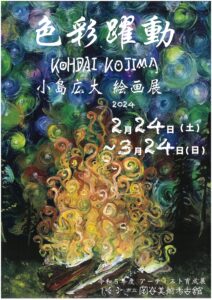

 版画家・武井武雄の故郷であり、信州の版画活動の原点ともなった「双燈社版画部会」が誕生したここ岡谷市は、昭和29年頃から版画教育についても盛んに行われるようになり、全国小中学校版画コンクールでの入賞者を輩出するなど、全国的にも注目を集めてきました。この伝統は受け継がれ、市民による版画制作、学校現場での版画教育は、現在でも広く行われています。
版画家・武井武雄の故郷であり、信州の版画活動の原点ともなった「双燈社版画部会」が誕生したここ岡谷市は、昭和29年頃から版画教育についても盛んに行われるようになり、全国小中学校版画コンクールでの入賞者を輩出するなど、全国的にも注目を集めてきました。この伝統は受け継がれ、市民による版画制作、学校現場での版画教育は、現在でも広く行われています。